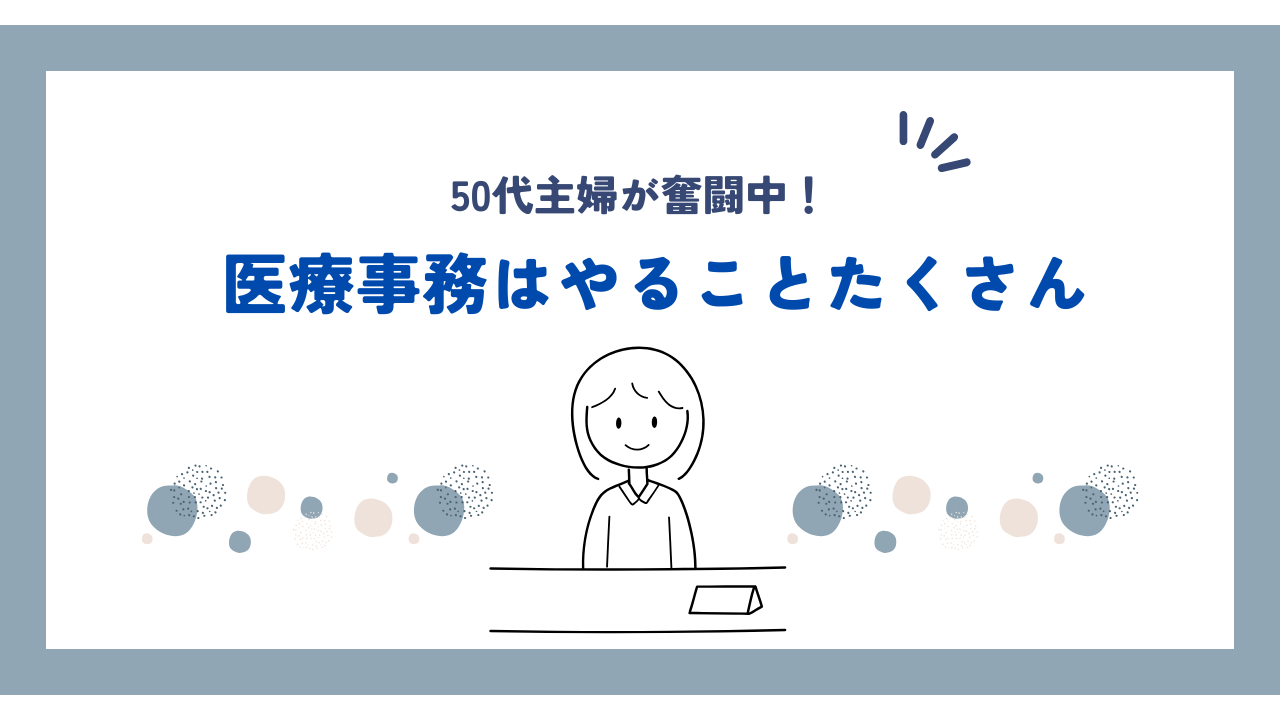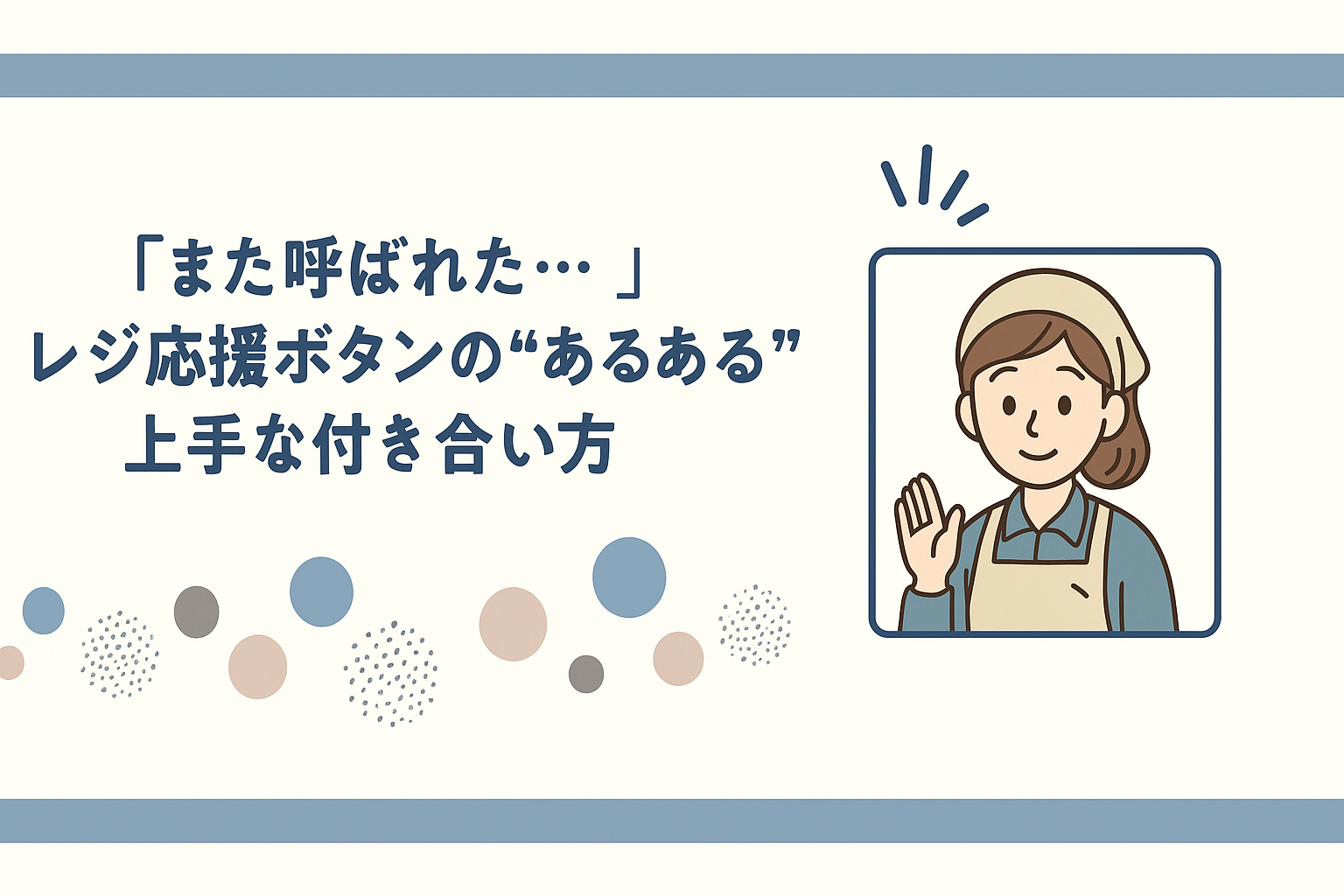医療事務の仕事って、受付や会計だけだと思っていませんか?
実は私も最初はそう思っていたんです。
でも、実際に働いてみてビックリ!毎日が
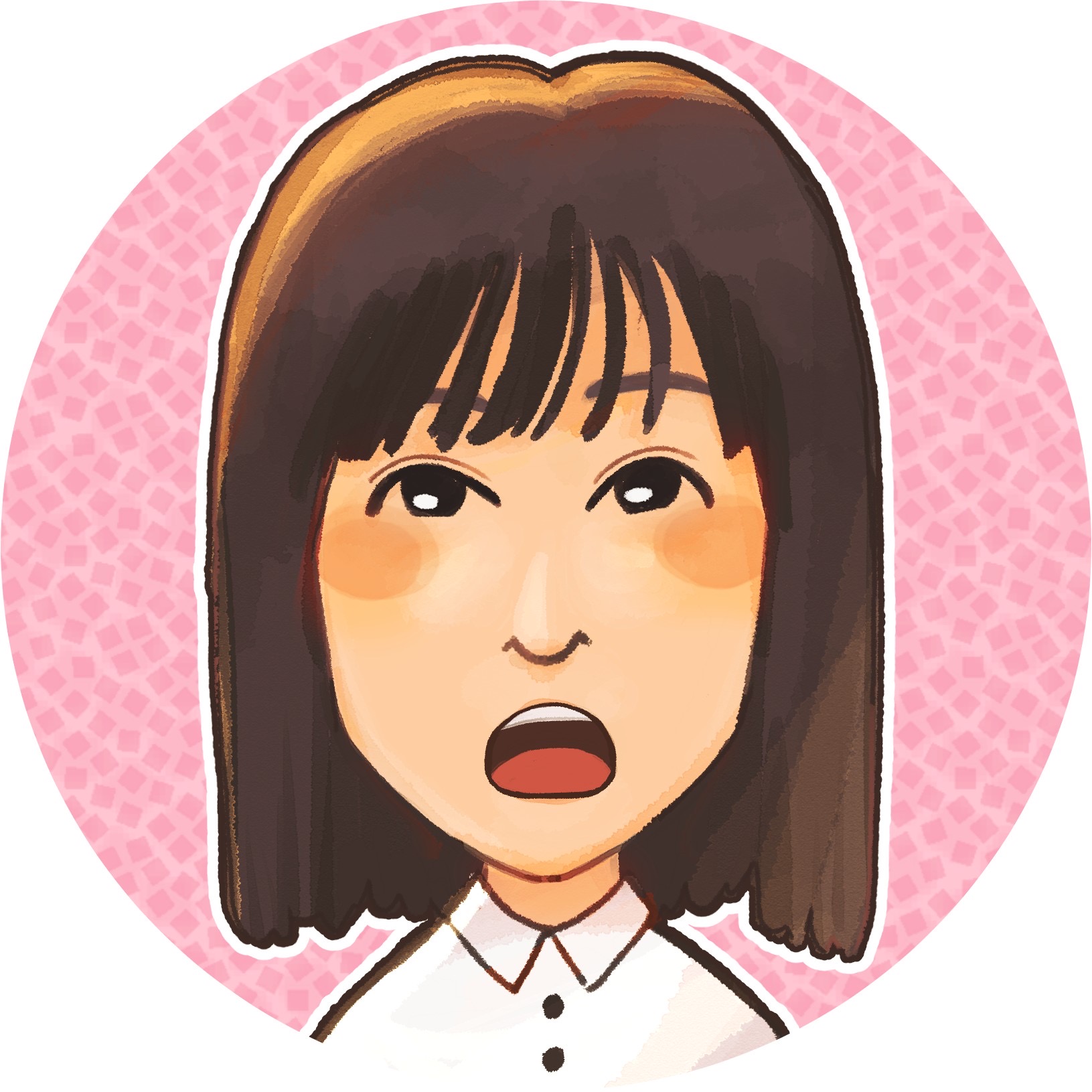
こんなこともやるの?
の連続でした💦
診察券を受け取って、保険証を確認して、会計をする…これが基本の流れです。
でも、それだけじゃ終わらないのが医療事務の世界。
患者さんの年齢や状況、市区町村の制度によって必要な書類も手続きもバラバラで、柔軟な対応力が求められます。
さらに、健診や予防接種、生活保護や難病の受給者証の確認、紹介状の管理や返書の準備、最近ではマイナンバーカード関連のトラブル対応まで…。
一日として同じ日はないくらい、さまざまな業務が飛び込んできます。
最初は戸惑うことばかりでしたが、少しずつ慣れていくうちに、

誰かのお役に立てているんだ…!
と実感できるようになりました。
今回は、そんな私が実際に経験した「医療事務のやることいろいろ」を紹介していきます!
医療事務の仕事あれこれ
📄保護券の対応は市によって違う
生活保護を受けている患者さんには『医療券』という書類が発行されます。
これがまた所属の市によって対応がさまざまです。
〇〇市はご本人が市の生活福祉課に申請をすることで医療券が発行されたり、△△市では市のホームページから申請用紙をダウンロードして記入し郵送だったりと自治体ごとに異なります。
また、「医療要否意見書」というものを提出する必要があり、通院の場合は最長6ヶ月です。
そして毎月チェックが必要です
医療券の確認ポイント💡
- ✅ 有効期限
- ✅ 診療科名
- ✅ 医療機関名
- ✅ 備考欄の内容(通院可・入院可など)
ご本人が医療券のことを理解されている場合は良いのですが、何も持たずに来院された時は福祉事務所に問い合わせる必要があります。
午後診察は、時間的に福祉事務所が閉所している場合もあるので焦ります。
まだギリギリ間に合う時間だったら急いで電話します。
年齢が若い方は、『次月から就業するので医療券は発行されない』ということもあるため、注意が必要です。
🍀特定健診は年齢や保険によって書類が違う
受診券を持って来院される方の対応もあります。
国民健康保険は市から、協会けんぽなどはそれぞれの健康保険から送付されます。
健診を受けられる方の年齢によって用意する書類も違い、問診票をもらって書いてもらう必要があります。
事前に記入したいと来院される方もいれば、当日で良いという方も。
当日来院されて思ったよりも記入箇所が多く小さな字なので、
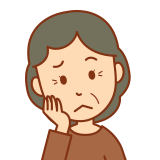
メガネを忘れたわ💦
と困っておられる患者様もいらっしゃいました。
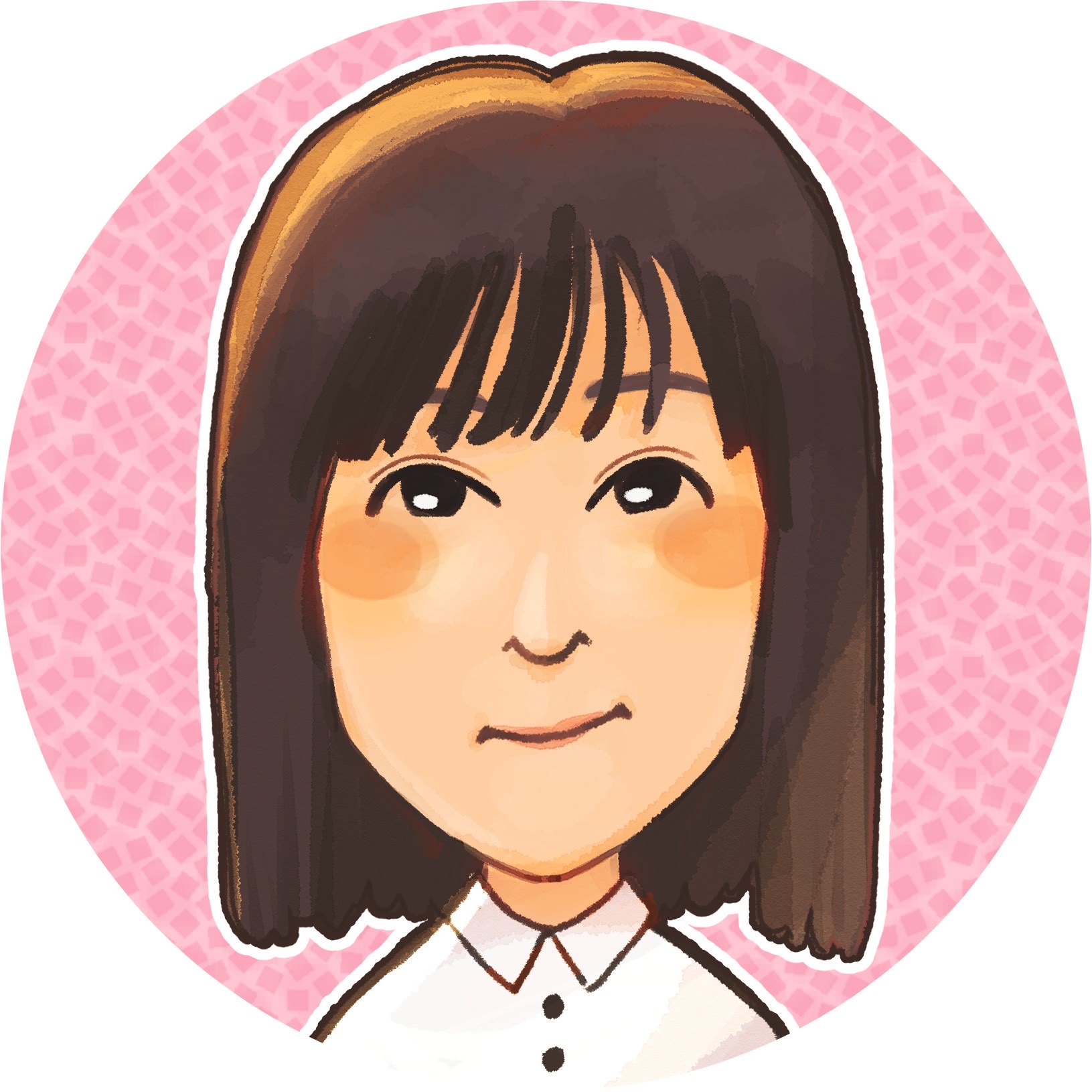
見えにくい文字は読み上げさせていただきますのでお声がけくださいね
クリニックによっては老眼鏡を置いているところもあるのは納得です。
健診は保険診療とは別扱いだから、会計の入力も少し特殊。
オプションの検診を受ける際には数百円の金額が発生します。
検診後に診察を受けたいという場合は、会計を別にする必要もあります。
最初のころは戸惑い、慣れるまでが大変でした。
何度も間違えては落ち込んで…でもそのたびに周りの方に助けられました。
💉予防接種の確認ポイントはここ!
予防接種も種類が多くて、年齢や対象によって助成の有無が違います。
例えばインフルエンザワクチン。
65歳以上は〇〇円のケースと、免除用紙をお持ちの方は無料のケースです。
市町村に請求書を作成する時も、それぞれ分けなければいけません。
滅多に接種されないワクチンはメーカーに在庫と入荷日を確認してから予約をとる必要があります。
予診票もメーカーさんに頼んで持ってきてもらうということを初めて知りました。
予診票の記入漏れや医師のサイン忘れなどがないか、ロット番号はちゃんと貼付されているかなど、しっかりチェックするのも医療事務の仕事です。
✉️紹介状の準備は大変
他の病院からの紹介状を持って来院された場合は、封を開けて受付ファイルに挿入します。
先生の指示でスキャンが必要な場合は、会計前にスキャンをします。
混み合っている時には、スキャンがうまくいかないと焦ることも。
当院からの紹介をする場合には、必要事項を記載してFAXをします。
近隣の総合病院によって受付方法も違うのですが、一番最寄りの総合病院では予約票が返送されます。
その予約票を持参して、患者さんは後日総合病院に来院するのです。
返送まで20分〜30分お待ち頂くことが多いです。
返書が必要な場合は、送り先の確認や切手の貼付、封筒の準備など事務的な作業も結構あります。
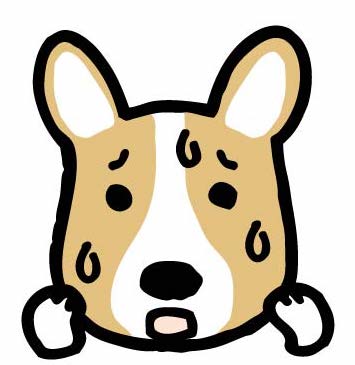
封筒、どこだ〜!
と探すこともしばしばです😅
焦っている時にかぎって見つからないんですよね。
🪪保険証期限切れとマイナンバーカード
最近はマイナ保険証が増えてきましたが、まだまだ紙の保険証も多く、期限切れに気づかず持参される方も。
期限切れの際は一旦自費でお支払いいただき、後日保険証を確認の上差額分を返金します。
マイナンバーカードが読み取れない、本人確認がうまくいかないなど、トラブル対応も少なくありません。
受付時の確認ポイント💡
- ✅カードリーダーの利用方法
- 患者さまがマイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに挿入します。カードにカバーが付いている場合は外す必要があります。
- 顔認証または暗証番号(4桁)の入力により本人確認を行います。顔認証ができない場合は暗証番号入力で対応可能です。
- ✅本人確認の方法
- 顔認証の場合、患者はカードリーダーのカメラに顔を向けます。眼鏡や帽子、マスクをしていても認証可能です。
- 暗証番号入力の場合、カード申請時に設定した4桁の数字を入力します。
- ✅同意事項の確認
- 過去の診療情報や薬剤情報、健診情報などを医師・薬剤師に提供するかどうかについて患者の同意を得ます。
- ✅診察券や公費負担医療受給者証の提示
- マイナンバーカードで保険資格確認を行っても、診察券や公費負担医療受給者証などは別途提示が必要です。
マイナンバーカードと保険証の両方をお持ちの場合は、マイナンバーカードの方がクリニックにとってはありがたいのです。
毎月『医療DX推進体制整備加算』のために月末に統計をとります。
利用率によって加算が3段階に分かれています。
さらに電子カルテに新規登録をする際もマイナンバーカードの方が圧倒的に楽で早いです。
学生さんは実家の住所と現在の自宅住所が違う場合があるので、電子カルテに『問診の住所』として入力をします。
👶こども医療証の落とし穴
こども医療証は、自治体によって紙タイプかプラカードかの形状が違います。
画像を読み取る際は圧倒的にプラカードの方が正確です!
でもクリニックの所在地である市のこども医療証は紙なのでほとんどまともに読み込めたことがありません。
こども医療は我が家の長女が小さい頃には『小学3年生まで』でした。
現在は『高校卒業する年の年度末まで』なので、実はこれがネックになることも…
高校生は1人で来院することも多く、こちらから声かけをしないとこども医療の提出を忘れてしまうことも多いんです。
1階の調剤薬局で気づいてくれて慌てて返金したこともありました。
まとめ
50代から未経験でスタートした私ですが、少しずつ覚えていく中で

医療事務って奥が深い…
と感じるようになりました。
正直、最初は不安の方が大きくて、覚えることの多さに圧倒される日々。
でも、ミスをしながらも少しずつ成長していく中で、患者さんに
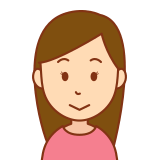
ありがとう!
と言ってもらえたり、先生やスタッフに頼ってもらえたりする場面が増えてきて、やりがいを感じるようになりました。
医療事務は、ただ受付や会計をするだけではありません。
たくさんの知識と気配りが必要な仕事であり、だからこそ、人の役に立てる実感が持てる仕事だと思います。

年齢的に新しいことを始めるのはもう遅いかも…
と迷っている方がいたら、私の経験が少しでも背中を押せたら嬉しいです。
これからも患者さんと医療をつなぐ大切な架け橋として、日々の積み重ねを大事にしながら、自分らしく頑張っていこうと思います!